
【正月準備】いつから始める?福を招くため12月29日にやってはいけないこととは?
今年も残すところあとわずか。みなさん、年末の大掃除の日程や年始の過ごし方はもうお決まりですか?
また、結婚して初めて正月を迎えるおふたりは、「マンションだけど、正月飾りをどこに飾ればいいの?」と悩む方もいらっしゃるかもしれません。
12月29日は、株式会社紀文食品が制定した「福の日」。新年に“福”を招くために、年末の準備を含めた正月の風習・行事についてまとめてみました。
- 目次
-
- クリスマスが終わったら正月準備スタート
- 12月29日に“やってはいけないこと”とは?
- 年神様のおもてなし?正月飾りを飾る理由
- 年神様を家に迎えるための正月飾り
- 門松・しめ縄・鏡餅の飾り方&飾る場所
- マンションの場合、鏡餅はどこに飾る?
- 正月飾りはいつまで飾る?片づけ方は?
- 正月飾りを片付けるのは「7日」や「15日」
- 正月飾りの片付け方とタイミング
- 鏡開きは11日・15日など地域によって異なる
- おふたりらしい正月準備で“福”を招こう!
※「福の日」とは?
12月29日は「福の日」という記念日。制定したのは、株式会社紀文食品。正月の食卓に欠かせない、おせち料理にも使われる練り製品でもおなじみの会社ですが、正月本来の意味やいわれを知ることで、福を招いてもらうのを目的としているそう。また、“29=ふく”と読む語呂合わせから、正月に備える準備を提案しています。
12月13日から「正月事始め」!
クリスマスが終わったら正月準備スタート

日本では、12月13日から「正月事始め」と言われる、正月を迎えるための準備期間に入ります。
この日以降、いつから正月の準備を始めてもいいとされている日のため、神社や寺院で煤払い(すすはらい)の行事や正月飾りの準備をする映像を観たことがある方もいらっしゃるはず。
一般家庭においては、年末に向けて仕事が忙しい時期でもあるので、実際には、クリスマスが終わった週末あたりから、新年の仕度を始めるという方も多いかもしれませんね。
12月29日に“やってはいけないこと”とは?
地域によって違いはあるものの、12月26日頃から正月飾りを飾り始めるのが一般的です。
ただし注意しておきたいのは、“9=苦”を連想させるという理由から、12月29日は、正月飾りの飾り付けを始める日には向いていないということ。大晦日の31日も、「一夜飾り」となり縁起が悪いため、避けたほうがよいそうです。
正月飾りは、クリスマス以降であれば28日か30日がベストと覚えておきましょう。
年神様のおもてなし?正月飾りを飾る理由

「正月飾り」と聞いて、みなさんはどんなものを思い浮かべますか?
結婚して自分の家庭ができ、住む場所が変わると、小さい頃にやっていた正月の風習や過ごし方にも変化が出ると思います。
住宅事情によっては、「実家の一軒家ではこうしていたけど、マンションでは正月飾りはどうするべき?」と悩む方もいらっしゃるかもしれません。そこで、正月飾りの飾り方や場所についてご紹介します。
年神様を家に迎えるための正月飾り

正月は、子孫繁栄や五穀豊穣をもたらしてくれる“年神様(としがみさま)”を家にお迎えして祀る行事です。
年神様は一年の幸福や健康をもたらしてくれる縁起の良い神様。年神様をお祝いして、たくさんの幸せを授けてもらうために、正月行事が誕生したと言われています。
諸説ありますが、正月飾りはいわば、年神様をお迎えし、気持ち良く過ごしてもらうための“おもてなし”の意味もあるようです。
門松・しめ縄・鏡餅の飾り方&飾る場所

地域差もありますが、一般的にお正月飾りと呼ばれるものは、「門松」「しめ縄」「鏡餅」の3つです。
いずれも、年神様をお迎えするために飾るものですが、現代では、マンションなど住宅事情によって門松やしめ縄は飾らないという家庭も少なくありません。多くの場合、手軽に購入できる簡略化した正月飾りを飾っているのではないでしょうか。

ちなみに、しめ縄は、ドアの内側に飾っても問題ないそう。住宅事情にあわせた正月飾りを探してみましょう。
| 門松 | 家の門の前などに立てられ、年神様の依り代(よりしろ)=“神霊が寄りつくもの”という役割をもっています。 |
|---|---|
| しめ縄 | 橙(だいだい)や譲り葉などの縁起物を飾り付け、年神様をお迎えするための神聖な場所であることを表します。玄関に飾り、邪気を防ぐ役割も。 |
| 鏡餅 | 年神様へのお供え物、かつ依り代と言われています。しめ縄と同じように、縁起物を飾り付けて、床の間や神棚に供えます。 |
マンションの場合、鏡餅はどこに飾る?

鏡餅は床の間や神棚に…というのが一般的ですが、先に書いたように、鏡餅は、年神様の依り代となるもので、お供えした場所に依りついてくださるため、家の中に複数お供えしてもいいそうです。
小さなサイズを複数お供えするのであれば、リビングや台所、子供部屋など、年神様に来ていただきたい場所に置いてみましょう。大きいサイズをひとつであれば、リビングといった家族が集まる場所で、玄関から一番遠い部屋に飾ります。
ただし、テレビ周りなどの騒がしい場所の近く、不安定な場所、床などの見下ろしてしまうような低い場所には置かず、整理整頓された高い位置にお供えするのもポイントです。
正月飾りはいつまで飾る?片づけ方は?
年末にしっかり大掃除を済ませ、正月飾りで年神様をお迎えして、お正月を過ごしたら、今度は、「正月飾りはいつ、どのように片づけたらいいの?」という悩みが出てきます。それぞれについてまとめてみました。
正月飾りを片付けるのは「7日」や「15日」
社会人であれば、「年始の仕事始めまでが正月」という印象を持つ方も少なくないはず。門松やしめ縄などの正月飾りを飾っておく期間を「松の内」と呼びますが、これは、地域によって差があります。
| 関東地域の松の内 | 1月1日~7日 |
|---|---|
| 関西地域の松の内 | 1月1日~15日 |
多くの場合が「7日」と「15日」に分かれますが、20日までという地域もあるようです。松の内が明けると年神様もお帰りになるため、正月飾りを片付けて、通常の生活に戻るというわけですね。

1月7日と言えば「七草がゆの日」。
春の七草(せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな、すずしろ)を使い、一年の無病息災を願って、7日の朝にいただくおかゆは、正月のごちそう三昧で過ごした胃腸を休めるという意味もあります。
正月飾りの片付け方とタイミング

神社では、「お焚き上げ」や「どんど焼き」といった、正月飾りを燃やして、年神様を空にお送りするための行事があります。それにあわせて、松の内が明けた8日、もしくは21日の朝、近くの神社に持っていき処分してもらいます。
神社に持参することが難しい場合でも、他のゴミと一緒には捨てず、大きな白い紙に、「左・右・中央」の順に塩を振り、お清めをしてから正月飾りだけを包み、各自治体のルールに従って出しましょう。
鏡開きは11日・15日など地域によって異なる

正月飾りのひとつ「鏡餅」は、松の内が明けた鏡開きに、大きなものは木槌などで割り、食べやすく小さくして、無病息災を願いながらいただくという風習があります。木槌を使う理由は、縁起物であるため刃物を使うのは縁起が悪いとされているためです。
鏡開きの日は、松の内が明ける日によって異なるようです。
| 松の内が「1月7日」までの地域 | 鏡開き「1月11日」 |
|---|---|
| 松の内が「1月15日」までの地域 | 鏡開き「1月15日」、または「20日」 |
ちなみに、15日は小正月、20日は二十日正月にあたります。鏡開きは上記以外にも地域差があるため、目安として覚えておきましょう。
結婚して初めての正月を迎える方へ
おふたりらしい正月準備で“福”を招こう!

結婚して初めて迎える正月、というおふたりにとって、季節の行事を通して地域の習慣の違いが見えてくるはず。こうした機会に、ぜひ、おふたりらしい正月の迎え方を見つけてみてはいかがですか?
正月飾りをすべてそろえるのはハードルが高い…という方は、自宅の大掃除を済ませた後、フラワーショップでも正月らしい飾りや草花のブーケなどが売っているので、それを飾るのもおすすめです。慌ただしくなりがちな年末に、心を落ち着かせ、癒しをくれる効果があるはず。
来年の福を招いて、家族が笑顔で過ごせるように、協力しあいながら余裕をもって年明けの準備を始めていきましょう!
<12月の記念日>
12月1日 手帳の日
12月3日 カレンダーの日
12月5日 アルバムの日
12月6日 姉の日
12月7日 クリスマスツリーの日
12月8日 ホールケーキの日
12月12日 漢字の日
12月13日 大掃除の日
12月17日 減塩の日
12月21日 遠距離恋愛の日
12月22日 スープの日
12月24日 クリスマスイブ
12月25日 クリスマス
12月29日 福の日
12月30日 地下鉄記念日
※記事内容を最新情報に更新しました(2024.12.19)
- この記事を書いた人
-
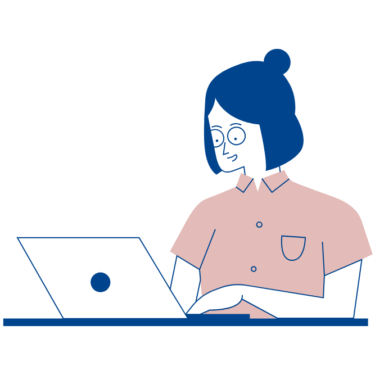
ライター さとう
女性誌WEBサイトのエディター&ライターを経て、フリーに。現在は、美容やライフスタイルを中心に女性向けの記事のインタビューも担当。
















